
継体天皇と坐摩神五柱(いがすりのかみ)を祀る、越前最古の歴史を有する神社。皇嗣となって越前を離れることとなった継体天皇が、自らの生霊を合祀して、馬来田皇女(うまくだのひめみこ)を斎主としたことが始まりとされています。
境内の樹齢350年のシダレザクラと参道のモミジは福井市の天然記念物に指定されています。特にシダレザクラは有名で、足羽山の代表的シンボルともいえる銘木です。美しく叙情的な桜を鑑賞するために毎年多くの人が足を運びます。

継体天皇と坐摩神五柱(いがすりのかみ)を祀る、越前最古の歴史を有する神社。皇嗣となって越前を離れることとなった継体天皇が、自らの生霊を合祀して、馬来田皇女(うまくだのひめみこ)を斎主としたことが始まりとされています。
境内の樹齢350年のシダレザクラと参道のモミジは福井市の天然記念物に指定されています。特にシダレザクラは有名で、足羽山の代表的シンボルともいえる銘木です。美しく叙情的な桜を鑑賞するために毎年多くの人が足を運びます。

春には「桜の名所100選」にも選ばれた3,500本の桜が咲き誇ります。茶屋で足羽山名物のこんにゃくや豆腐の田楽に舌鼓を打ち、お酒をいただきながら満開の桜を眺めて風流なときを過ごすこと。
これが春の楽しみのひとつとなっています。
初夏には散歩道沿いに植えられている14,000株ものアジサイ(福井市の市花)がしっとりと美しく花開きます。
その道は「あじさいロード」と呼ばれ、訪れる人々の目を楽しませてくれます。
散策やジョギングに最適な憩いの場です。

1909(明治42)年、皇太子(のちの大正天皇)の行啓を機に、公園として整備され始めました。園内にはフィールドアスレチックとミニ動物園を備えた足羽山公園遊園地、福井の自然に関する資科を一堂に集めた福井市自然史博物館などがあり、お子様連れにも人気の遊び場です。
平和塔・継体天皇像、数十基にもおよぶ古墳群が太古の歴史に思いを馳せることができます。市内を展望できる名所などが点在していて、のんびりした散策には絶好のロケーションとなっています。

建物は大正末期の古典主義的なデザイン。現存している希少な鉄筋コンクリートの洋風建築物です。装飾的柱型など手の込んだ造りは、建築技術史的にも興味深く、館内には当時のドイツ・シーメンス社製のポンプや当時の道具などがそのまま残されています。



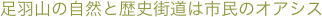




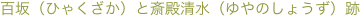
たのしみは朝おきいでて昨日まで無かりし花の咲ける見る時 橘曙覧
汐ならで朝な夕なに汲む水も辛き世なりと濡らす袖かな 志濃夫迺舎歌集

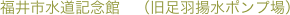
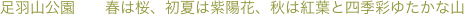
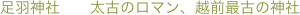
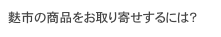
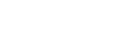

Copyright © 2006 Fuichi.
足羽山茶屋「木の芽屋」前の桜
足羽山茶屋「大久保茶屋」の紅葉
愛宕坂にある橘曙覧記念館


上の句は平成6年、天皇皇后両陛下のご訪米の際、アメリカのクリントン前大統領が歓迎スピーチで引用したことで有名な「独楽吟(どくらくぎん)」の一首です。
句の作者である幕末の歌人・橘曙覧が居を構えた黄金舎(こがねのや)跡があります。その後、料亭・五獄桜(ごがくろう)を経て、
現在は橘曙覧記念文化館となっています。
記念館の横から百坂に続く道、横坂があります。ここからは福井市内が一望できます。下は毎朝横坂を通って斎殿清水から水を運ぶ妻の苦労を詠んだ句です。

最近では毎年春、愛宕坂では足羽山の春の風物詩「灯の回廊」が行われます。
愛宕坂から足羽神社まで、横坂、水道記念館を行灯で幻想的にライトアップ。100個の和ろうそくの行灯が、笏谷石の階段を照らします。情緒あふれる風情の美しい灯りが人々を春の宵の道へと誘います。

百坂の横に昔あった泉は、今から約500年前発見されました。夏は冷たく冬は温かい水が豊かに
湧き出ており、住民の最高の飲み水としてたいへん重宝されていました。
古くは、足羽神社のご神水として毎朝お供えされたことから斎殿清水(ゆやのしょうず)と呼ばれ、
ご神水を運ぶ道として百坂(百段坂)が整備されました。夏は白玉・ところ天・金時などの店が並び、
絶好の納涼場として大変にぎわいました。
ところが、大正13年福井市の水道ポンプ場建設にともない由緒ある御清水を埋め立てすることに
なりました。その後建立された清水観音では、現在も毎年8月18日に祭礼が行われます。
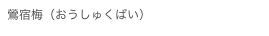
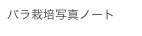
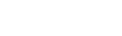
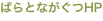
店舗の横にある麩市自慢の
ローズガーデン。バラ栽培のようすを日誌と写真でつづっています。
麩市の店先にある樹齢150年の
老梅です。毎年たくさんの花を
咲かせてくれます。
麩市の商品は量販店への卸しを
ほぼしておりません。お求めの際は、
麩市オンラインストアを
ぜひご利用ください。